2013年12月27日
いじられキャラ?
こんにちは ビオラのAです。
本日は、年末の暇つぶしになればと、オーケストラ関連の面白い話を考えていたのですが
オケ+ネタといえば避けて通れないのが「ビオラジョーク」。
ビオラ弾きだからこそ書ける話題かと思います、年末年始の暇つぶしにでもご一読ください。
まず、ビオラジョークをご存じない方のために、いくつかご紹介します。
-世の中には2種類のビオリストがいる。下手なビオリストと、死んだビオリストだ。
-なぜビオラの楽譜はアルトクレフなんですか?
-違う音を弾いていることが、ほかの楽器奏者にばれないためです。
-バッハ先生がカノンを作曲するに至った理由は?
-2人のビオリストがユニゾンで弾いているのを聞いたそうです。
-バイオリンが盗まれないようにするにはどうすればいいですか?
-ビオラケースに入れましょう。
興味のある方は ビオラジョーク で検索してみてください、人生嫌になるほど出てきます♪
ビオラがオーケストラ・ジョークの笑いネタというのは、伝統的なオケの通例(?)です。
これについて、バイオリニストのマクシム・ヴェンゲーロフ氏などは、「なぜビオラがこれほど笑いネタになるのか」と憂慮しておられますが、一般的にビオラ奏者はそう迷惑がっていないようで。ここらへんがビオラに落ちる理由なのかもしれません。
では、いつからビオラがジョークのネタになったのか。
作曲家エクトル・ベルリオーズは、1844年の著書 「管弦楽法(Treatise on Instrumentation)」で、ビオラおよびビオラ奏者について、以下のように述べています。(抜粋+解説)
----------------------------
《 ビオラについて 》
ビオラは、バイオリンよりも5度低く調弦された楽器で、楽譜はアルトクレフで記される。奏法は前チャプターで述べたバイオリンのそれと同様であるため、ぶっちゃけ5度低いバイオリンという考え方もできる。 他に類のない独特のメランコリックな響きをもつ楽器であるにもかかわらず、オーケストラにおいてはメロディを1オクターブ低く弾くとか、ベースラインを1オクターブ高く弾くといった、非常に残念な扱いを受けている。
だがこれには理由がある。
まず18世紀の作曲家の多くはビオラをどう扱っていいかわからなかった。当時ハーモニーといえば3混声が主流であったため、4番目のビオラの扱いに困った作曲家はメロディあるいはハーモニー、ひどい場合は両方混在のオクターブ弾き、という荒業を躊躇なくビオラに課した。
18世紀(1701~1800年)
また、残念ではあるが当時ビオラ譜に複雑なパッセージを盛り込むことはほぼ不可能だった。なぜなら当時 ビオリストはあまり上手でないバイオリニストから選ぶのが一般的だったため、結果としてバイオリンもビオラも弾けない奏者がビオラを担当するのが常であったのである。
現在(1844年)においても、このビオラに対する暴挙は存在する。一流のオーケストラにおいてさえ、バイオリニストよりも技量のあるビオリストは未だ少ない。しかしこの冷遇による実害は徐々に認知されつつあり、ほんの少しずつではあるが改善傾向にある。
-----------------------------
もとバイオリン弾きとしては耳の痛い内容ですが、この事実をバッサリ指摘できたのはベリオーズ先生くらいのものでしょう。ようするにジョークは事実だっ
ビオラは、楽譜は誰も読めないアルトクレフなのに楽器はフリーサイズという、非常に個人主義な楽器です。
フリーサイズが行き過ぎて、昔はこんなビオラもあったようで。
バッハが愛したビオラ・ポンポーサ(写真はウィキペディアより転載)

こんなの弾いてたのも、ジョークネタになった理由のひとつかもしれませんね。
-*-*-*-*-*-
2nd violinのIから補足です。
併せて槇原敬之さんの「ビオラは歌う」を検索してみてください。
ちなみに、NHKみんなのうた でも登場しました。
でも登場しました。
本日は、年末の暇つぶしになればと、オーケストラ関連の面白い話を考えていたのですが
オケ+ネタといえば避けて通れないのが「ビオラジョーク」。
ビオラ弾きだからこそ書ける話題かと思います、年末年始の暇つぶしにでもご一読ください。
まず、ビオラジョークをご存じない方のために、いくつかご紹介します。
-世の中には2種類のビオリストがいる。下手なビオリストと、死んだビオリストだ。
-なぜビオラの楽譜はアルトクレフなんですか?
-違う音を弾いていることが、ほかの楽器奏者にばれないためです。
-バッハ先生がカノンを作曲するに至った理由は?
-2人のビオリストがユニゾンで弾いているのを聞いたそうです。
-バイオリンが盗まれないようにするにはどうすればいいですか?
-ビオラケースに入れましょう。
興味のある方は ビオラジョーク で検索してみてください、人生嫌になるほど出てきます♪
ビオラがオーケストラ・ジョークの笑いネタというのは、伝統的なオケの通例(?)です。
これについて、バイオリニストのマクシム・ヴェンゲーロフ氏などは、「なぜビオラがこれほど笑いネタになるのか」と憂慮しておられますが、一般的にビオラ奏者はそう迷惑がっていないようで。ここらへんがビオラに落ちる理由なのかもしれません。
では、いつからビオラがジョークのネタになったのか。
作曲家エクトル・ベルリオーズは、1844年の著書 「管弦楽法(Treatise on Instrumentation)」で、ビオラおよびビオラ奏者について、以下のように述べています。(抜粋+解説)
----------------------------
《 ビオラについて 》
ビオラは、バイオリンよりも5度低く調弦された楽器で、楽譜はアルトクレフで記される。奏法は前チャプターで述べたバイオリンのそれと同様であるため、ぶっちゃけ5度低いバイオリンという考え方もできる。 他に類のない独特のメランコリックな響きをもつ楽器であるにもかかわらず、オーケストラにおいてはメロディを1オクターブ低く弾くとか、ベースラインを1オクターブ高く弾くといった、非常に残念な扱いを受けている。
だがこれには理由がある。
まず18世紀の作曲家の多くはビオラをどう扱っていいかわからなかった。当時ハーモニーといえば3混声が主流であったため、4番目のビオラの扱いに困った作曲家はメロディあるいはハーモニー、ひどい場合は両方混在のオクターブ弾き、という荒業を躊躇なくビオラに課した。
18世紀(1701~1800年)
また、残念ではあるが当時ビオラ譜に複雑なパッセージを盛り込むことはほぼ不可能だった。なぜなら当時 ビオリストはあまり上手でないバイオリニストから選ぶのが一般的だったため、結果としてバイオリンもビオラも弾けない奏者がビオラを担当するのが常であったのである。
現在(1844年)においても、このビオラに対する暴挙は存在する。一流のオーケストラにおいてさえ、バイオリニストよりも技量のあるビオリストは未だ少ない。しかしこの冷遇による実害は徐々に認知されつつあり、ほんの少しずつではあるが改善傾向にある。
-----------------------------
もとバイオリン弾きとしては耳の痛い内容ですが、この事実をバッサリ指摘できたのはベリオーズ先生くらいのものでしょう。
ビオラは、楽譜は誰も読めないアルトクレフなのに楽器はフリーサイズという、非常に個人主義な楽器です。
フリーサイズが行き過ぎて、昔はこんなビオラもあったようで。
バッハが愛したビオラ・ポンポーサ(写真はウィキペディアより転載)
こんなの弾いてたのも、ジョークネタになった理由のひとつかもしれませんね。
-*-*-*-*-*-
2nd violinのIから補足です。
併せて槇原敬之さんの「ビオラは歌う」を検索してみてください。
ちなみに、NHKみんなのうた
 でも登場しました。
でも登場しました。




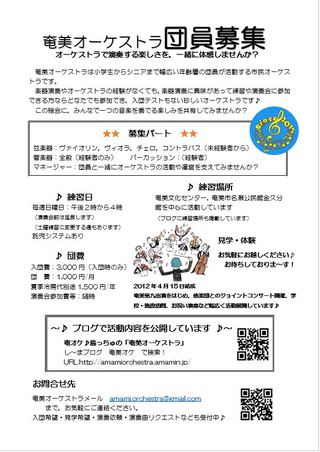



ふと思い出したのはyou tube の下記演奏画像。
私のなかではViolistは研究熱心で真面目そしてユーモアも忘れない方々。
だからいじられキャラに?よろしければ見て下さいませ。
本年もどうぞよろしくお願いします。
http://www.youtube.com/watch?v=uub0z8wJfhU
明けましておめでとうございます!
ビオラの素敵な動画のご紹介、ありがとうございます。
いいですね~大人ですね~。一生に一度でいいから、こういうスマートなブチキレをしてみたいものです。
ビオラの演奏も素晴らしくて。。。このくらい美しい音色を響かせられたら、「大きいバイオリン」 という世間の認知度も変わっていくのでしょうけれど、皆様の心を魅了するには、まだまだ修行が足りないようで。
話は変わりますが最近、ソプラノ歌手のフローレンス ジェンキンスという方にはまっております。
音痴すぎて有名になった歌姫なのですが(YOUTUBEで出てきます)、最初は聞けたものではないと思ったアリアが、何度か聞くうちに、見事な音の外しっぷりにすっかり泥酔してしまいまして。
これこそが音の魔力、まさに「音楽」だなと。
音を外す外すとジョークのネタにされ続けるビオラですが、外れた音にこそ、ディープでヘヴィーな魅力が隠れているのだと最近、ゆがんだ自己満足に悦しております。
またヘンな所で話をビオラにつなげてしまいましたが、今年もどうぞ宜しくお願いいたします!